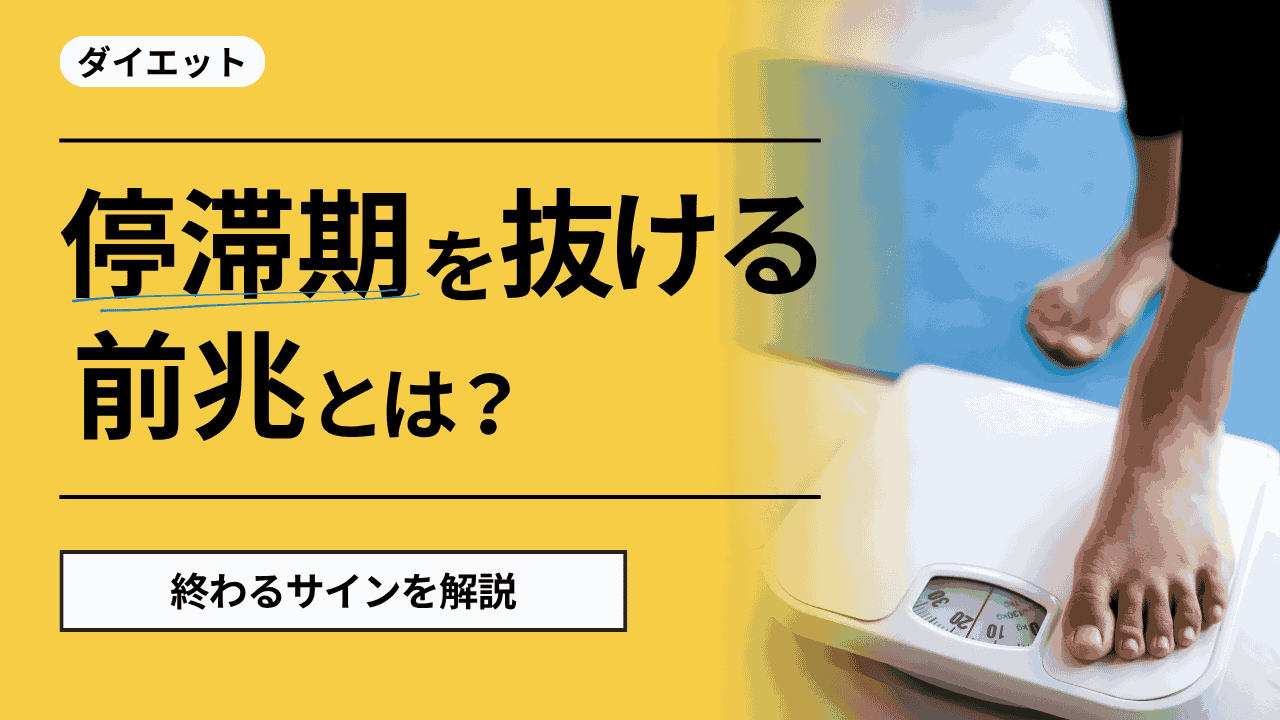ダイエットを始めると、多くの人が1度は経験する体重が減らなくなってしまう停滞期。
毎朝体重計に乗っても数値が変わらず、焦りや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
停滞期を抜ける際には、体重のほんの少しの変動や強い空腹感、むくみの改善などが見られることもありますが、残念ながら明確な前兆はこれまで確認されておりません。
体重減少が止まってしまうのは体の防衛本能であるホメオスタシス機能が原因で、カロリー制限を開始してから約1週間程度から代謝の調整が始まっていることが研究でわかっています。
停滞期は人によって大きく異なり、筋肉量が少ない人や過去に極端な食事制限を経験した人は長引く傾向があります。
食生活の見直しや週に2〜3回の筋トレなど代謝を上げる取り組みを組み合わせることで、停滞期から抜けるのをサポートしてくれる可能性もあります。
この記事では、停滞期を抜ける前兆や停滞期を早く終わらせる方法、乗り越えるためのモチベーション維持法について解説していきます。
ダイエットの停滞期とは?

ダイエットの停滞期とは、これまで順調に落ちていた体重がふいに伸び悩んでしまう状況のことです。
多くのダイエット経験者の方がこの停滞期に悩まされたことがあるかと思います。
この停滞期のメカニズムは体の安全装置であるホメオスタシス(恒常性維持機能)という機能によるものです。
この停滞期について理解を深めることで、焦らず適切に対処できるようになるでしょう。
この停滞期は個人差はありますが、体重の5~10%程度落ちたあたりで発生することが多いと言われています。
また、停滞期は一度だけでなく何度か繰り返すとも言われており、長期的な視点でダイエットに取り組むことが大切です。
停滞期とは防衛反応(ホメオスタシス)が働く状態
ダイエットの停滞期は、減り続けていたはずの体重の減少が一時的に止まる現象で、体の防衛反応であるホメオスタシスが原因です。
大阪体育大学の情報によると摂取エネルギーが消費エネルギーよりも少ない状態が続くと、体はエネルギーが不足しないようにエネルギー消費量を少なくする適応が起こります。
これは生命維持のための正常な反応といえるでしょう。
愛知県医師会によると体重が減少すると、脳の弓状核が食欲を亢進させエネルギー代謝を減少させることで体重を一定に保とうとします。
ホメオスタシスによる代謝適応は、ダイエット開始後1週間程度から既に始まることが研究で明らかになっています。
この防衛反応を理解することが、停滞期を乗り越える第一歩となります。
リバウンドと停滞期の違い
停滞期とリバウンドは、体重変化の方向性が正反対の現象です。
停滞期は体重減少が一時的に止まる状態を指しますが、リバウンドは減量後に体重が元に戻る、または以前より増加する現象を意味します。
停滞期中は摂取カロリーと消費カロリーが釣り合った状態になりますが、リバウンドは摂取カロリーが消費カロリーを上回ることで起こるのが特徴でしょう。
停滞期は継続的なダイエット中に起こる一時的な現象ですが、リバウンドは多くの場合ダイエット終了後の食生活の乱れが原因となります。
両者を正しく理解し、適切な対処をすることが長期的な体重管理には欠かせません。
停滞期が来るタイミングには大きな個人差がある
停滞期が訪れるタイミングは人によって大きく異なり、特定の時期を断定することは困難です。
研究データによると、カロリー制限開始後わずか1週間で既に代謝適応が178±137kcal/日程度起こることが確認されています。
一般的に体重の5〜10%が減少した段階で停滞期に入るとされることが多いですが、これも個人の体質や減量ペースによって変わるでしょう。
基礎代謝量、筋肉量、ホルモンバランスなど複数の要因が停滞期のタイミングに影響します。
自分の体の変化を注意深く観察し、焦らずに対処することが重要になります。
停滞期は1度だけでなく繰り返す
ダイエット中の停滞期は、1回だけということはほとんどなく、何回も繰り返すことが多いです。
体重が段階的に減少していく過程で、体は新しい体重に適応しようとするため、減量と停滞を繰り返しながら目標体重に近づいていきます。
最初の停滞期を乗り越えても、さらに体重が減少すると再び代謝適応が起こり、新たな停滞期に入る可能性があるでしょう。
停滞期の頻度や期間は、減量ペース、体脂肪率、運動習慣などによって変わってきます。
この繰り返しのパターンを理解しておけば、2回目以降の停滞期でも冷静に対処できるようになるはずです。
停滞期を抜ける前兆は?終わるサインを解説
停滞期を抜ける前兆については、多くのダイエット経験者から様々な体験談が報告されていますが、科学的に証明された明確な前兆は現時点では確認されていません。
体重の微細な変動、空腹感の変化、むくみの改善など、いくつかの兆候が観察されることがありますが、これらは個人差が大きく、必ずしも全ての人に当てはまるわけではありません。
前兆があるかどうかにこだわるのではなく、むしろ停滞期になってしまったとしても、正しい食事や運動をきちんと続けることが一番大切です。
焦らずに、長い目で自分の体の変化を見守るのが大切です。
それではまずは、前兆らしきものがあるといわれる方の経験談から、その可能性と注意点も含めて考えてみましょう。
体重が徐々に落ち始める
体重のわずかな変動を、停滞期を乗り越えたサインのひとつとして紹介していますが、これが断言できる科学的なサインであるとは言えません。
たとえ0.1〜0.2kg程度と小さな変動でも、そのうちの0.1kgでも体重が増減すると、停滞期が終わりに近づいている合図かもしれません。
しかし、体重変動とホルモン濃度の間に相関関係はないという研究結果もあるため、これはあくまでも当事者の感覚をもとにした話だと思います。
日々、体重測定を同じ条件で行い、週単位の体重変動を見ることで、停滞期から脱出できたかどうか確認しやすくなりますね。
ちなみに、体重という数字は水分量や便の量にも影響されるため、体重に一喜一憂せず長い目で見ることがオススメです。
強い空腹感を感じるようになる
停滞期の終わり頃に空腹感が強くなった経験があるという声はよく聞かれますが、それに関連する科学的根拠は現時点ではありません。
代謝が活性化してくるとエネルギー消費量が増え、空腹感は強まります。
レプチンやグレリンといった食欲調整ホルモンバランスが変化することで、空腹感の感じ方も変わることがあるでしょう。
しかし、強い空腹感が栄養不足を訴えている合図であるケースもあるので、適切な栄養摂取に努めることが必要です。
空腹感の感じ方は個人差が大きく、空腹感が強くなったからといって必ずしも停滞期を脱出できるわけではないことを知っておきましょう。
むくみがとれて体が軽く感じる
停滞期の間にたまった余分な水分が排出され、むくみが改善され、体が軽く感じられることがありますよね。
むくみがとれて水分バランスも整っている状態だと、見た目も変わり、体重以上にスッキリした印象を周りに与えることがあるでしょう。
塩分摂取量の調整や適度な運動により、リンパの流れが改善されることも、むくみ解消につながります。
しかし、むくみがとれているだけで実際には脂肪が落ちていない可能性もあります。
体の軽さを感じることは、モチベーション維持には役立ちますが、停滞期脱出の確実なサインとは言い切れません。
必ずしも停滞期を抜ける前兆があるわけではない
停滞期を抜ける際に、明確な前兆を感じない人も多くいます。
科学的には体重減少とホルモン値の間に関連性がないことから、前兆の有無は個人差が大きいと言えるでしょう。
急に減り出すこともあれば、徐々に変化していることもあります。
前兆を感じられなくても、食事と運動の管理を続けていれば、やがてこの停滞期は終わります。
前兆にとらわれすぎず、長期の視点でダイエットを続けることが成功への近道でしょう。
停滞期を早く終わらせる方法
停滞期を早く終わらせる方法は必ずしも存在しませんが、基礎代謝を維持し体に刺激を与えるいくつかの方法があります。
過激な方法は裏目に出てしまうこともあるため、無理のない範囲で行うことが大切です。
食事内容を見直したり、計画的にチートデイを設けたり、十分な水分補給・睡眠を意識したりと、様々な要素を組み合わせて実行することで、停滞期を脱するきっかけになるかもしれません。
しかし、これらの方法も人それぞれ効果には個人差があることを認識し、体調を第一に実践することが大切になります。
以下に科学的な見地から対処法とその効果について説明して参ります。
栄養素やカロリー摂取量の見直しをする
停滞期を早く終わらせる方法としては、まずは栄養バランスと摂取カロリー量に見直しを図るのが効果的です。
過度のカロリー制限は逆に基礎代謝を下げてしまいかねないので、基礎代謝量を最低限確保できる範囲でのカロリー摂取が求められます。
そして、そのうち特にたんぱく質の割合を体重1kgあたり1.2〜1.6g程度を目安に意識して摂取することにより、筋肉量の維持へと繋がっていくでしょう。
主要栄養素の目標摂取量は以下のとおりです。
- たんぱく質:体重1kgあたり1.2〜1.6g
- 炭水化物:摂取カロリーの45〜65%
- 脂質:摂取カロリーの20〜35%
- ビタミン・ミネラル:推奨量通りに
ビタミンやミネラルなど微量栄養素の不足もまた代謝低下の要因となるため、積極的に野菜や果物を摂取していくことが望ましいです。
食事内容を定期的に記録すると客観的に栄養バランスを評価できるので、停滞期を脱するきっかけが掴める場合もあります。
チートデイを導入する
チートデイは一時的に摂取カロリーを増やすことで代謝を刺激する方法ですが、その効果は限定的である可能性があります。
研究によると、チートデイによるレプチン分泌の増加や代謝量の回復は一時的な現象で、通常の食事に戻るとすぐにベースラインまで低下することが分かっています。
チートデイを設けた減量が、設けない減量より脂肪燃焼効果が高いという科学的証拠は現時点では存在しません。
それでも、精神的なストレス軽減やモチベーション維持の観点から、計画的なチートデイは有用かもしれません。
週1回程度、通常の1.2〜1.5倍のカロリーを摂取する程度に留め、暴飲暴食は避けることが賢明でしょう。
適切な水分量をたもつ
ダイエット中の停滞期対策には、適切な水分バランスを計ることが非常に重要です。
1日の水分摂取量の目安は、体重1kgあたり30〜35mlが理想的とされています。
不足すると代謝も落ち、不要な老廃物を排出する役割を担っているリンパなどの排泄機能も低下してしまいます。
運動で汗を大量にかいた日には、その分の水分補給をしなければなりません。
さらにカフェインやアルコールには利尿作用がありますので、これらを飲んだあとは必ず水分補給をしておく必要があります。
例えば、朝起きてすぐ、お昼になっていないことを確認して、運動前に飲んだり、運動後に飲んだりと、水分補給のタイミングを決めておけば、安定して水分補給が出来るでしょう。
質のよい睡眠を取る
7〜9時間の質の高い睡眠は、ホルモンバランスを整え、代謝機能を正常に保つために不可欠です。
睡眠不足はコルチゾールの分泌を増加させ、脂肪の蓄積を促進する可能性があります。
成長ホルモンの分泌は深い睡眠中に最も活発になるため、睡眠の質を高めることが脂肪燃焼にもつながるでしょう。
就寝2〜3時間前の食事や激しい運動は避け、寝室の温度を18〜22度程度に保つことで、良質な睡眠環境を整えられます。
規則正しい睡眠リズムを確立することで、停滞期からの脱出を促進できる可能性があります。
停滞期が長い人はどんな人?
停滞期の長さには個人差があり、体質や過去のダイエット経験、生活習慣などが大きく影響します。
筋肉量が少ない人、繰り返しダイエットを行ってきた人、極端な食事制限をしたことがある人などは、停滞期が長引く傾向があります。
また、運動パターンが単調な人や、むくみ・便秘などの体調不良を抱えている人も、停滞期が長期化しやすいでしょう。
これらの特徴を理解することで、自分に合った対策を立てることができます。
停滞期が長い場合でも、焦らず適切な方法で対処することが重要です。
筋肉量が少なく基礎代謝が低い人
筋肉量が少ない人は基礎代謝が低く、停滞期が長引く傾向があります。
筋肉は安静時でもエネルギーを消費する組織であり、筋肉1kgあたり約13〜20kcal/日の基礎代謝があるとされています。
体重減少に伴い筋肉量も減少すると、さらに代謝が低下して停滞期が長期化する可能性があるでしょう。
基礎代謝と筋肉量の関係を以下に示します。
- 筋肉1kgあたりの基礎代謝:約13〜20kcal/日
- 脂肪1kgあたりの基礎代謝:約4.5kcal/日
- 筋肉量10%減少時の基礎代謝低下:約50〜100kcal/日
筋力トレーニングを取り入れることで、筋肉量の維持・増加を図ることができます。
週2〜3回の筋力トレーニングと適切なタンパク質摂取により、基礎代謝の低下を最小限に抑えられるはずです。
過去に何度もダイエット経験がある人
繰り返しダイエットを行ってきた人は、体が飢餓状態を学習し、より強い防衛反応を示すようになります。
ヨーヨーダイエットと呼ばれる体重の増減を繰り返すと、体は次の飢餓に備えて脂肪を蓄積しやすくなるでしょう。
過去のダイエット経験により、レプチン感受性が低下している可能性もあります。
このような場合、通常より緩やかな減量ペースを設定し、体重の5%程度の減量ごとに維持期間を設けることが効果的です。
長期的な視点で体質改善に取り組むことが、停滞期の短縮につながります。
極端な食事制限の経験者
1日の摂取カロリーを基礎代謝以下に制限するような極端なダイエットは、強い代謝適応を引き起こします。
研究によると、カロリー制限により代謝量は筋肉量と脂肪量の減少から予測される以上に低下することが明らかになっています。
極端な糖質制限や特定の栄養素を排除する方法も、体内のホルモンバランスを乱す原因となるでしょう。
過度の食事制限により甲状腺ホルモンの分泌が低下すると、基礎代謝がさらに低下します。
バランスの取れた食事に徐々に移行することで、代謝機能の回復を促すことができます。
有酸素運動のみで身体が慣れてしまった人
同じ強度・時間で有酸素運動ばかり行なっていると、身体が効率良くエネルギーを使えるようになり、消費カロリーが減ってきます。
ランニングやウォーキングなど同じ運動ばかり行なっていると身体は適応しやすいため、結果停滞期が長引く可能性もあります。
また消費カロリーは体重とともに減っていくことも理解しておきましょう。
筋力トレーニングやHIIT(高強度インターバルトレーニング)など他の運動を行なうことで身体の運動への適応を防ぐことができます。
毎週トレーニングの強度や種類を変化させることで、身体にいつも新しい刺激を与え続けることができます。
むくみや便秘がある人
むくみや便秘は体重の停滞を引き起こし、実際の脂肪減少を見えにくくする要因です。
体内に余分な水分が蓄積されると、体重計の数値は変わらなくても、実際には脂肪が減少している可能性があります。
便秘により腸内に老廃物が蓄積すると、1〜2kg程度の体重増加につながることもあるでしょう。
塩分の過剰摂取、運動不足、水分不足がむくみや便秘の主な原因となります。
食物繊維を1日20〜25g摂取し、適度な運動と水分補給を心がけることで、これらの問題を改善できるはずです。
停滞期を乗り越えるモチベーション維持の方法は?
停滞期はつらい時期ですが、モチベーションを上手く維持していければ、乗り越えられます。
まずは体重だけを見て焦らずに、自分の成長をいろいろな角度で確認していくことも大切になります。
わかりやすいグラフ化や日記や目標変更などの方法をうまく組み合わせていければ、停滞期でもポジティブな思考を維持していけるでしょう。
そして何より、いま停滞しているのはいつか必ず抜けられる一時的なものだと理解し、長い目で見て今の自分の成長を信じることです。
では、具体的にはどのようにしてモチベーション維持していけば良いのか、記載しています。
停滞期でもグラフをつける
体重の変化をグラフにしておくと、停滞期に突入しても、微妙に変わっている部分を確認できるのです。
日々の中での変動に一喜一憂せず、日・週・月単位の傾向をつかむことができます。
体調はもちろんですが、体重、体脂肪率、ウエストサイズなど、いろいろな指標を書いておくことがポイントです。
効果的なグラフ記録の項目をご紹介します。
- 体重(毎日朝一)
- 体脂肪率
- ウエスト・ヒップサイズ(週1回)
- 運動内容と時間
- 食事内容の概要
振り返りたくなったときもグラフを見返すと、きっと過去の成功体験を思い出されるのではないでしょうか。
また、スマートフォン等のアプリを使えば、自分で入力した数字が勝手にグラフ化されるので、数値の変化をグラフで視覚化したいというニーズにもお応えできます。
一行日記の活用をする
毎日一行でもいいのでその日の体調や気分、食事の満足度などを書いておくと、また、停滞期中のストレスが軽くなります。
感情やら体調の変化を書けば、客観的に自分の状態を確認できるようになるはずです。
停滞期中の小さな成功体験、例えば階段が楽に上れた、いつもより服がきつくなくなったなど、書いていくことも重要です。
書きたいことが多い日には、たとえネガティブな内容でも構いません。
書き続けるうちに、自然と前向きな内容が増えていくものです。
1ヶ月後に読み返すと、確実に前進している実感が得られるはずです。
目標の再設定をする
停滞期になったら、まず今の目標を見直し、より自分にあった、現実的で達成できそうな目標に切り替えるタイミングです。
ダイエットであれば、ひたすら体重ばかりに目を向けるのはよしとして、せめて体脂肪率の減少や運動習慣がついた、食生活が改善したなど複眼的目標を掲げるといいです。
短期と長期の目標を切り替えて考え、段階的に達成していくことがポイントでしょう。
まずは体重が変わらないことに焦点をあてず、野菜摂取量を増やす、夜更かしをしないなど、自分の健康の為にできることを目標にするのをオススメします。
達成できたら自分へのご褒美を考えてみましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医学的助言ではありません。個人差が大きいので専門家に相談して下さい。